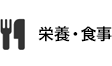がんやがんの治療が妊孕性に与える影響~女性編~
将来、子どもが欲しいと考えていても、がんやがんの治療によって妊孕性(妊娠できる可能性)が低下し、妊娠・出産が難しくなる場合があります。妊孕性への影響は、治療の内容や期間、患者の年齢などによっても異なります。がんの手術、薬物療法、放射線治療による女性の妊孕性への影響には、主に、下記のようなものがあります。がんの告知を受けた直後は、病気と向き合うだけで精一杯だと思いますが、将来的に後悔しないように、自分が受ける治療の妊孕性への影響を知っておくことが大切です。
① 手術による影響
女性の場合、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんなどで、子宮と両方の卵巣を摘出しなければならない場合には、妊娠・出産ができなくなります。子宮と片方の卵巣が残せれば妊娠・出産が可能なことが多いものの、患者の年齢、あるいは手術による血流障害の影響で、卵巣機能が低下し不妊になることがあります。
子宮頸がんで妊孕性が残せるのは、円錐切除術、広汎子宮頸部摘出術などで子宮を温存できるときです。子宮体がんでは、一般的に、子宮と両方の卵巣・卵管を全て摘出するのが標準治療ですが、子宮内膜異形成増殖症、または、がんが子宮内膜にとどまっていて(子宮の筋層へ入り込んでいない)、腫瘍の顔つきがおとなしいタイプ(高分化型)の類内膜がんG1相当、または子宮内膜異型増殖症で、妊娠・出産希望がある場合には、ホルモン療法をすることで子宮と卵巣の温存が検討されます。
大腸がんなどの消化器がんにおける骨盤内手術で、卵巣と卵管、子宮と卵管というように骨盤内の臓器同士が癒着したり卵管がふさがったりすると、排卵後の卵子の通り道が閉ざされ、妊娠しにくくなることがあります。
② 薬物療法の影響
がんの薬物療法中に妊娠すると胎児に影響が生じる恐れがあるため、治療中とその後数カ月は避妊が勧められます。抗がん薬の中には、卵子や卵巣機能に大きなダメージを与えるものと、影響が少ないものがあります。妊孕性への影響は、薬の種類や投与量、患者の年齢によっても異なりますが、治療期間中に卵子数が減少し、その後、生涯に渡って卵巣機能に影響を及ぼす可能性のある治療薬によって無月経になる確率は、30~76%です。生涯に渡って卵巣機能に影響を及ぼす恐れがあることがわかっている治療薬には、シクロホスファミド、ブスルファンなどのアルキル化薬やシスプラチンなどの白金製剤などがあります。治療後に無月経になって不妊になるリスクは、治療期間が長く薬の使用量が多いほど、また、治療を受けたときの年齢が高いほど高まります。
一方、乳がんの再発予防のために実施される術後ホルモン療法は5~10年間と長期間に渡るため、治療後に妊娠・出産をしたいと考えたときには、年齢的に難しい場合もあります。妊娠・出産のためにホルモン療法を中断するかどうかは、担当医と十分話し合い、慎重な判断が必要です。現在、早期乳がんの患者が妊娠・出産のためにホルモン療法を中断することによる影響を調べるための国際共同研究(POSITIVE試験)の結果が待たれています。
③ 放射線治療の影響
卵巣や子宮、腹部や骨盤への放射線照射は、卵巣内の原始卵胞数を減少させ妊孕性を低下させます。放射線照射の回数や線量、患者の年齢によっても不妊のリスクは変わってきますが、総被ばく量が増えるほど、あるいは、年齢が高くなるほど、治療後に閉経となって妊娠・出産ができなくなるリスクが高まります。一般的には、月経が始まる前の小児で15グレイ(Gy)、月経のある10代女性では10グレイ、成人女性では6グレイを超えた放射線を腹部や骨盤に照射すると、治療後に卵巣が機能しなくなり、妊娠・出産ができなくなるリスクが高いとされます。
また、造血幹細胞移植の前処置として行われる放射線の全身照射、脳腫瘍に対する40グレイを超える頭蓋照射も、卵巣機能や性ホルモンの分泌能にダメージを与え、永久的に不妊になるリスクの高い治療です。
参考文献:
「小児,思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017 年版」(日本癌治療学会編)
「乳癌患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療ガイドライン2021年版 第3版」(日本がん・生殖医療学会編)
参考サイト
日本がん・生殖医療学会